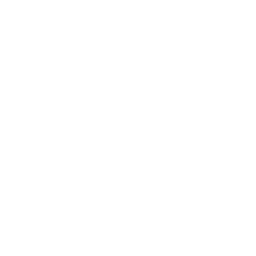111件のひとこと日記があります。
2021/09/29 08:29
平松さとし氏の記事を見て、海外遠征を考える
ヤフーニュースで平松さとし氏の記事を読んだ雑感です。
「欧州の馬場は本当に重いのか? 先入観を捨てないと、凱旋門賞は見えてこない」
https://news.yahoo.co.jp/byline/satoshihiramatsu/20210929-00260047
最初の感想は「ではJCの世界レコードをヨーロッパで塗り替えてください」であった。
しかし、よく読んでいろいろ調べると、「先入観を捨てないと、凱旋門賞は見えてこない」という部分は勉強になったし、「欧州の馬場は本当に重いのか」も「極端ではない」という意味合いでは納得できる部分もある。
記事冒頭のフォレ賞の世界レコードであるが、レコードが出た理由はG1であること、そしてコース形態が大きい。
G1となればレースレベルも上がり、時計も出やすい。日本には1400のG1は存在しない。
大きいのはコース形態だ。JRAのコース紹介によると、ロンシャン1400mは引き込み線からのスタートとなっている。そしてこれは、ちょうど登りが終わって下り坂スタートになるのだ。そしてカーブも非常に緩やかで、見るからに時計は速くなりやすい。
ただ、「皆がイメージしているほど重くはないのだ」と述べているように、軽いとは言ってはいないので、わからない主張ではない。
記事のその後で凱旋門賞のファウンドの勝ちタイム2分23秒6に触れ、「“時計を要す馬場は日本馬に向かず、速ければ日本馬向き”という単純な構図は成り立たないのではないだろうか」と述べている。これは昔から芝の長さについて指摘があり、日本に比べ2倍長いため、パワーが要求されるというものである。デジタル的に言えば、早い時計で走るためのパラメーターが異なるという事であり、この指摘自体は納得できるものだ。
ちょっと異議があるのは結論の部分である。
欧州馬は強いから世界中で通用している、はさすがに無理があるのではないか。
私が本コラム内で指摘された馬を見て思ったのは、海外遠征のノウハウについてである。
まず凱旋門賞で好走した日本馬、エルコンドルパサー、ナカヤマフェスタ、オルフェーヴルの4頭は、全て調教師が海外遠征の経験があったのである。
レジェンドのシーキングザパールもそうだし、タイキシャトルの藤沢調教師は欧州で調教助手の修業を積み、欧州競馬をよく知っている方だ。エイシンヒカリのみ、あまり経験が豊富で無かったようだ。
そういった目線でドバイシーマクラシックのここ6年の勝ち馬を見ると…調教師は大物がずらりと並び「海外遠征?ノウハウは当然ありますよ」といった感じがする。
また、血統からも賞賛のあるレースに使っていることがわかる。
欧州色が強いのはJack HobbsとDolniyaの2頭。Hawkbillは父Kitten's Joyや母系の血統から、機動力と底力のある北米血統。そしてPostponed、Mishriff、Old Persianの3頭は全て父がDubai Millenniumの系統である。
Dubai Millennium自身がドバイワールドカップの勝ち馬で、Dubawiを筆頭にこの系統は適性が非常に高い。こうしてみると、欧州の調教師たちは「強いから行く」のではなく、「適性があるから行く」という考えの方が強いのではないだろうか。
実際、Hawkbillは欧州2400mでは少し勝ち切れない部分はあったし、DolniyaはドバイシーマクラシックがG1初勝利である。
思えば欧州は最も競馬の歴史が深い国であり、海外遠征のノウハウも深い。世界中で活躍できる下地が整ってるのではないだろうか。
このことから、海外遠征は挑戦する陣営の質が最も重要であると考える。
今回凱旋門賞に挑戦する日本馬についても少し。
クロノジェネシスの斉藤崇史調教師は今年ドバイで調教師として初めて海外に遠征、松永幹夫厩舎時代にレッドディザイアでドバイに遠征している。欧州だとまた違うのかもしれないが、初めててない分期待はできる。
大久保龍志調教師は今回が初めてのようだが、見事フォア賞を獲った。本番も期待したい。
正直、馬の適性には疑問があるが、現役馬では最も適性がある2頭が挑戦してるのは間違いない。朗報を期待したい。