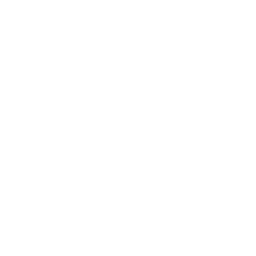99件のひとこと日記があります。
2020/05/23 22:12
冷戦
今回の新型コロナの騒動ではっきりしたのはこれからの世界は米中の二色に分かれるということ。
一帯一路を言い出したあたりから中国の影響力ははっきり表面化してはいましたが、日本も含め、金で懐柔させられて痛い目を見た国が多いこと。
月の開発勢力争いもあるし、東シナ海でのあれこれもあって米中の対立激化は避けられない。
そもそも中国共産党の覇権主義はいまに始まったことでは無い。ウイグル自治区や香港でのことを考えれば誰にでもわかる。
日本も二足の草鞋の政策では立ち行かなくなる可能性が高い。我々の決断力が問われる局面は近い。
-

てつさん
アレキさん
おっしゃる通りです
世界一位の国と二位の国の間で三位の国として舵取りをしていますが
板ばさみがどんどんきつくなり外圧が強まると、次に何が生まれてくるのか
アメリカ人も中国人も利を重視するので、まだ平行線は続くかもしれませんが
コロナで状況の変化が加速した気はします -

てつさん
中国人と日本人が似ているかと言うと、古くから文明の影響があったので部分的には似ているけど違う部分もかなりあると思っています
中国の影響を受ける前の時代もあったし地理的に海を隔てていたので日本オリジナルな部分は当然あるでしょう
その日本の独自性、いい所悪い所を鋭く捉えたのは小室直樹氏だと思いますが、彼は戦勝国に押し付けられた自虐史観による教育のため、人々は正当性も誇りも持てないでいると言っていますね
中国人もなかなか複雑ですが、素直ないい人もかなり多く、それゆえ共産党が一定以上の支持を得てしまっています
周辺のベトナムやラオスも共産主義国ですし
あれの本質は一党独裁だと思いますが、それが実は国民性に合っているのかも知れません -

アレキさん
馬もそうじゃないですかね。才能あっても体格体力めぐまれてても環境変わるとまるっきり走れなくなる子、競馬しろと促されても闘争心をまるで湧かさない子。
よいもの持ってても走らないことに地団駄します。「強制的に投げ出されるサラブレッド社会、それを生きてくのに最適な性格を子に伝える天才」がサンデーサイレンスでした。(決して「血統のレベル」なんてものは上がってはいない。)
人の技術が進歩して、環境が整備されて、走りやすくはなる。
けど走るかは競馬場に向かう馬の気持ち次第。
科学が進歩して、環境が整備されて、生活が便利にはなる。
けど幸せと思うかは社会に向かう人の気持ち次第。
私も石川は住みよいと聞きます。
仕事こそ忙しくても抗う私の心は飽いている。
POGでもなんでも、暇なら、かかってきてくださいな。 -

アレキさん
ペペロンジュースさん
学生時代に優る社会人生活を送ってる人の方がまれ、と申しますか、そんな人この世にどれだけいるものかというのが世の中(社会)かと。
ですから社会で生きていくために学生時代がある、とも言える。「探究」したものは遊びだろうと勉強だろうと夢想だろうと「身についている」、その学びをどう生かすか。LV1、ただし敵も弱い、と都合よく始まりませんね。なかには恵まれた人もいらっしゃいますが基本、みんなもがいてるようにみえます。
だからこそ内省しつつ「身につけたもの」を生かすサイエンスが人生かな?と思います。 -

アレキさん
コロナ見なくてもネット競馬みてたらわかります!
とくに運営が同調圧力の権化のような舵取りしますもん…
ありえないっす -

アレキさん
まあ、「考える力」が養われたところでこの「美しい国ニッポン(笑)」が欧米みたく権利だなんだとゲバゲバしい国になるのもアレですが…。
日本がまちがってるからと外国が正しいとも思いませんし…
“ちょうどよい塩梅”ってのを考えられないんですかね、人類というのは。
…だからどこまでいってもどうちぎっても働きアリの法則を守り人は何世紀も越えていて人のままなのかも知れませんが。 -

アレキさん
てつさん
なるほどですね。思想教育にも理屈より実感の下地が必要だとみれば、この島国では災害こそ世界まれにみる社会主義精神(なかでも、プラスは協調性、マイナスは同調圧力へ)の伝道者の役割を果たしてきたのかも知れません。逆に外圧(敵意)にさらされるとナショナリズムや自立心(考える力)が芽生えると…。
考えてみると日本が外圧を受けたとき、日本に新しい学問・思想が芽生え、強すぎる同調圧力をともなって右につくか左につくかとやってますもんね。元寇こそ押し返しましたけど、免疫のなかった幕末明治から昭和初期は本当にドタバタでした。
ただ振り返るとそれがまた新しい色どりをこの国に生んで…
日本は染められたい女みたいな国なんですかね。 -

ペペロンジュースさん
おっしゃる通り、日本の和というのは戒律ありきのものです。学問という自由の中で説かれたものではない。
ただ、海と山をどこからでも眺められる土地ですから、自然現象に否応なく注視できる環境ではあった。街のど真ん中に誇るように建つ教会とは違って、木々の中に奥まった暗がりに建つ神社。奥ゆかしさを愛するのも日本人らしさなのかもしれない。
winter windではなく、日本人はそれを木枯らしと表現する。なんともまぁしみじみ。。 -

ペペロンジュースさん
てつさん
日本と中国の暮らしの文化は全く真逆をいってますからね。
日本ではここの村に戒律があって、田畑や葬式まで全てにおいて協力の体制が敷かれてましたが、中国はいつどこに引っ越そうが、何しようが、問題なかったみたいなんですよね。
それって割と大きい違いでしょう?社会構造と文化思想体系に関連性があると仮定するなら。
孔子はあくまで学問の中で説いたので、もしかしたらその思想の真髄が一般民衆にまで届いていないのかもしれません。キリスト教やイスラム教、仏教などとは違い、宗教観という名の宇宙観が中国では漢字がそれに当てはまりますし、始皇帝前の時代では国々によって異なる宇宙観がありましたから。
今の中国が、土地によってどれくらい人間性が異なるのかはわかりませんが、偉大でありながらも、ここまで拗れた国は他にないでしょうね。 -

ペペロンジュースさん
なんかその話を聞いた時に嫉妬したのをよく覚えている。
クリエイティブな才能は自分には全く欠けてますから(笑)