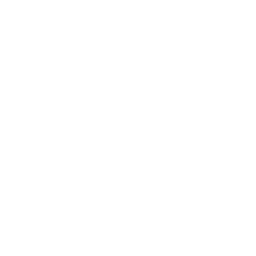11件のひとこと日記があります。
2018/08/31 17:56
プロフェッショナル【武豊】
【第五章 追う】
先ずは武豊騎手と20年以上も親交のある作家の著書から一部を紹介。
「馬上で豪快な動きをすると『追い方が上手いから勝った』と言われ、反対に負けると『馬を邪魔したから負けた』と言われる。対照的な武の乗り方は、追う時には背中を馬体と水平にしたまま動かさず、リズミカルな肘の屈伸で馬の首の動きを補助し、ストライドを伸ばす手助けをする。つまり武は、自分の体以上に馬の首や四肢を大きく動かしているのだ。空気抵抗を減らし、馬が走りやすいところから重心を動かさずストライドを伸ばす動きをサポートしてやる...という機能を徹底的に追求した結果、フォームが美しくなる」
これに加えて下半身が非常に安定している。若い頃はもう少し膝を締めて多少窮屈な感じを受けた。それが幾度となく海外遠征を繰り返しているうちに海外騎手の騎乗技術を研究し、それを自分なりに取り入れてきている。その中でも大きく影響を受けたのがC.マッキャロンの乗り方を参考に、馬を追う時あえて支点を作らず、自転車で手放し運転をするように乗るようになったことが現在の追い方に繋がっているようだ。それは膝を多少開き気味にし、プラス鐙の長さを若干長くして下半身の稼働域を増やしている(現在ではまた短めにしているようだ)。その下半身の動きはくるぶしに伝えられ、馬の走りを促している。武豊騎手の場合、馬体に触れているのは左右のくるぶしだけ。時折アクシデントに見舞われた時にはふくらはぎが接触することもあるが、殆どの道中や追い出した時の下半身はくるぶしのみで馬をコントロールしている。これも子供の頃に馬術を経験していたからこその技術ではないかと思える。馬術の場合は殆ど鞭を使用せず、競走馬よりも長くした鐙に掛けてある両足のかかと若しくはくるぶし、そして手綱でコントロールしている。それが活きているのだろう。
又、ヨーロッパの騎手達を参考にすると良く分かると思う。ヨーロッパの騎手達は鞭を多様している様に見えるが、鞭の使用については日本より早くから使用制限されている。その為、時折鞭で馬体を叩く、あるいは擦る程度で、大きく体を前に動かした時にはまるで風車鞭の様に見せ鞭を使用している。大きく上体を動かしてはいるが、鞍に臀部をドンとつくようなことはしない。これらを自分の騎乗方法に上手く取り入れているのが武豊騎手なりの追い方だ。
馬の背中にトントンと臀部をつけると背中を痛めると言われているが、確かに一理ある。それは...トモの力が強くてもそれを引き上げなければ強い蹴りを得られない。そこで必要なのが背中(背筋)である。そして馬の下半身が余程強くなければよれてしまうことになる。それでなくともスタミナが限界に近いラストでは、馬は相当な負担を強いられている。できるだけ馬に負担を掛けないように乗ることも騎手の役目でもある。又、そのレースで良い結果が出ても、馬が負担を強いられて嫌がるようにならないとも限らない。そうなると次走からは良績が望めなくなる可能性だけではなく、故障の原因にもなりかねない。だからこそ余力がなくなってきている馬や明らかに四肢の運びのバランスが悪い馬、そして鞭で叩かれたり強く追われることを嫌がる馬を強いて追うことは避けている。こうしたことまで考慮して追っているのが武豊騎手である。
但し、トントン乗りが全てにおいて悪いとは限らない。特に国内のダートは海外よりも砂の部分が深く乾いたダートでは脚抜けが悪い。海岸の砂浜を思い出していただくと分かるが、乾いた部分は足がめり込み非常に力を必要とする。反面、波打ち際の砂は海水によって締まり走りやすくなる。だからこそ良馬場のダートはタイムが遅くなるということが分かる。そして国内のダートコースを作るに当り、基準が定められている。三重構造だったと思うが、一番上が砂である。その一粒毎のサイズは忘れてしまったが、必ず丸くしなくてはならない。その理由の一つとして、跳ね上げられた砂によって人馬に怪我をさせないということから定められている。こうしたダートで良績の結果を残すには、馬術と似たトントン乗りが効果的な場合もある。地方競馬を見れば多くの騎手がそのトントン乗りを取り入れている。それが良いか悪いかは判断しがたいが、馬の背中に臀部をドスンと落とすような騎手はあまり見られない。武豊騎手も同様にトントン乗りは取り入れているが、それはあくまで前へ移動させ小さな動きで効率良く馬に伝えているからこそ、見た目にはわからない技術と言える。