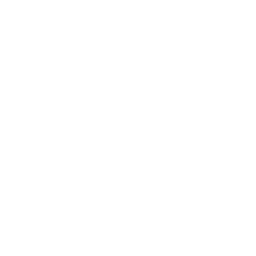150件のひとこと日記があります。
2011/12/29 19:25
備忘録3
では、馬に投資した場合を考えてみましょう。
先の騎手のコメントに従うと、馬は着順の趨勢に対して70%もの影響力を持ってることになるかと。
馬の能力を開発したり解放しやすくなるよう尽力した場合、その効果はこれほど広い範囲で作用するのです。
しかも、馬は調教方法を間違えなければ騎手の騎乗成功確率よりも遥かに高い確率で指示どおりの能力を発揮します。
ようはあちらと比較にならないほど確実性が高いのです。
さらに、馬の能力向上は不可能な騎乗を可能にもします。
場合によっては騎手のミスですらチャラにできることもある。
トップジョッキーが魅せる鮮やかな差し切り勝ち。
決まれば「さすが○○は違う」とファンはその手綱捌きを讃えます。
でもちょっと待ってください。
その騎乗、ホントに○○さんじゃなきゃ不可能だったのでしょうか?
着順への貢献度はお馬さんの方が高いのに、こちらの頑張りは見てもらえないのでしょうか?
思い返してください。
外人騎手は、馬が完調一歩手前のトライアルレースでは、明らかに格下の馬では、トップハンデの馬ではどんな成績おさめてますか?
彼らはそもそも結構良い馬に乗っていませんか?
調教師の多くは勝負レースで外人騎手を起用します。
そういうレースに出走する馬はもともと能力が抜けていたり、メイチに仕上げられています。
僕は良い馬に乗ってるなら、勝って当たり前なんじゃないかと思います。
馬の能力の開発・解放に係る改善効果は多岐に渡ります。
調教負荷の向上による生理的ポテンシャルの改善、矯正器具の装着による気性の改善、調教パターンの変更による走行フォームの改善、戦略的出走計画の実行による適鞍の早期把握などなど。
その効果はここに挙げた例に留まらず、多岐に及ぶことでしょう。
ここまで来れば分かりますよね?
成績改善を期待するなら、騎手よりもこちら側、つまり厩舎の仕事領域(調教や路線選択etc.)に注目した方がより現実的であるということに。
そもそも騎手はミスを犯すもの。
個別の騎乗機会でのミスを一々指摘してたらキリがありません。
ミスをする度に先のリスクを犯してまで騎手変更を繰り返すメリット、ほんとにあるのでしょうか?
誰の眼でも分かるような駄騎乗を繰り返すジョッキーならリストラされて当然ですが…。
皆が矛先を向けてるジョッキーが本当にそのタイプなのか?
当該レースの騎乗ぶりのみならず、過去の騎乗ぶりや馬の臨戦過程、ライバルとの力関係などなど、様々な方向から敗因を分析する。
こういうステップを踏まなきゃ騎手が敗戦の主犯だったかなんて分かりゃしないと思うんですけどね。
騎手はミスが目立つポジションにいるから戦犯にされやすいけど、着順は騎手のミスだけでなく当時の馬の能力などの総体からなることを認識しておかないと。
馬券が外れた時は「○○氏ねーーーっ!!」と叫んでサッパリ忘れましょう。
(→次に続きます)