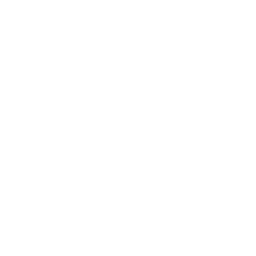367件のひとこと日記があります。
2016/04/30 20:47
予想コラム [No.034] 5/1(日)京都11R天皇賞(春) その1
今週の俺の旅は、明日天皇賞が行われる京都。今、嵯峨野にある小倉百人一首殿堂時雨殿というところにいる。
実は速攻で淀へ・・・といきたいところだったが、せっかく久しぶりの京都なので、いくつかの名所旧跡を巡りながら、天皇賞予想のヒントをつかもうと考えた俺。
まず《京都、天皇》というワードから思いつくのは京都御所。しかし残念ながらここはフリーで見学できるシステムではない(事前予約が必要)ということで×。なのでその後平安神宮、二条城、マイナーだが桂にある天皇の杜古墳・・・etc.と巡ってみたのだが、どこもレース予想のヒントになる符号が見えてこない。そこで視点を変え、「天皇の文化参入を探るってのはどうだ?歴代の天皇なら、例えば和歌とか詠ってるのが残ってるだろ?」ということで、あの有名な百人一首に目を付けたわけだ。
小倉百人一首。知らない人のために簡単に説明しておこう。
平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した公家・藤原定家(1162-1241)が選んだ秀歌撰である。これは元々、鎌倉幕府の御家人で歌人でもあった宇都宮蓮生という人が、京都嵯峨野に建築した別荘・小倉山荘の襖の装飾のため、定家に色紙の作成を依頼したところから始まる。定家は、飛鳥時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、100人の歌人の優れた和歌を一首ずつ選び、それを年代順に1番から100番まで番号を付けて色紙にしたためた。できた当時にはこの襖の歌集は「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」「小倉色紙」などと呼ばれたていたが、後に定家が小倉山で編纂したという由来から、「小倉百人一首」という通称が定着した。室町時代後期、連歌師の宗祇が著した『百人一首抄』(宗祇抄)によって研究・紹介されると、小倉百人一首は歌道の入門編として一般にも知られるようになった。さらに江戸時代に入り、木版画の技術が普及すると、絵入りの歌がるたの形態で爆発的に庶民に広まり、以降現在に至るまで人々が楽しめる遊戯・競技としても普及したのである。現に今も広瀬すず主演の公開中映画『ちはやふる』で、この小倉百人一首はあらためて注目を浴びている。
さて話を戻す。天皇賞とのつながりを考える上で、100首のうち「天皇の詠んだ歌」は重要なキーとなるはずである。探したところ実はあまりなく、現役としての天皇が詠んだのが3首、退位した元天皇が詠んだのが5首のみだったが、それぞれの意味と共に、その醸し出すイメージが今回の天皇賞のそれと合致しているか、および作者の実際の人物評で、◎○▲△×の5段階で評価してみた。
【現役天皇】
01天智天皇 秋の田のかりほの庵の苫をあらみ我が衣手は露に濡れつつ
《秋の田圃のほとりにある仮小屋の、屋根を葺いた苫の編み目が粗いので、私の衣の袖は露に濡れていくばかりだ。》
※イメージ・・・秋の豊穣(▲)、郷愁(○)、静けさ(○)
※作者寸評・・・大化の改新を成し遂げ、即位後も政治的に辣腕を発揮した傑人(◎)
02持統天皇 春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山
《いつの間にか春が過ぎて夏がやってきたようですね。夏になると真っ白な衣を干すと言いますけど、あの天の香具山にあのように衣がひるがえっているのですから。》
※イメージ・・・初夏の快晴(◎)、色彩感(○)、爽やかさ(◎)
※作者寸評・・・数々の政変の中、皇后から天皇になり精力的に活躍した女帝(○)
15光孝天皇 君がため春の野に出でて若菜摘む我が衣手に雪は降りつつ
《あなたにさしあげるため、春の野原に出かけて若菜を摘んでいる私の着物の袖に、雪がしきりに降りかかってくる。》
※イメージ・・・初春の野原(▲)、透明感(○)、やさしさ(◎)
※作者寸評・・・政治的手腕もあり、文芸にも秀で、当時としては長寿であった(○)
ふむ。3首とも、ポジティブな雰囲気の歌だ。