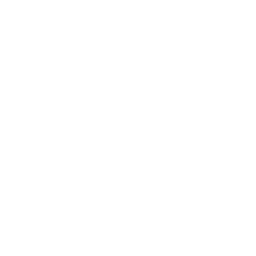367件のひとこと日記があります。
2016/09/03 19:06
さようなら新潟記念 その3
(第2章の続き)
そんな数多くの中州のうち最も紛争の火種だったのが、のちに流作場新田(図の橙色箇所)と呼ばれる中州である。この中州も先述のように水深の関係で新潟町の所有ということで幕府の沙汰が着いたのだが、その後50年ほどするとどんどん沼垂町側に肥大し、ついには沼垂町側が信濃川の本流だったのにそこが浅瀬になってしまい(古信濃川)、新潟町側が本流に変わった。さあそうなると黙っていないのが沼垂町民。『こらぁもう、水深測るまでもねーろ、俺らの土地らねっか?』と意気込んだのは当然で、1747年に再びこの中州の所有権を求めて訴訟を起こす。ところが新潟側も『おめーたちゃ、50年前にお上が決めたことをなーんしてほじくり返す?もう俺らのモンだすけな!』と反撃。そして幕府の結論は新潟町側の言い分を認め、沼垂側の上告を却下したのである。ああ、沼垂の不運は続く。さらに時を前後して阿賀野川がまた氾濫し流れが変わってしまい、沼垂湊のところの阿賀野川は水量が激減したため湊としての機能が低下するというツキの無さもあった。
その後・・・ここからは大幅に端折る(笑)。
19世紀に入り新潟町側の信濃川にさらにまたくつかの中州ができ肥大化し(図の緑色箇所)、そこにも人が住むようになって新潟町の規模は広がり湊もさらに発展した。この中州は現在の礎町、毘沙門町、湊町といったあたりである。
1844年、流作場新田は幕府領となる。
1858年、日米修好通商条約により、日本の開港5港のうちの1つとして新潟湊が選ばれる。いっぽう沼垂の方は湊の機能的にも劣っていたので、もはや新潟のライバルではなく「大新潟港」の一部、つまり補助的な扱いに甘んじるようになる。
ところが鼻高々だった新潟町も、1868年に北越戦争、1880年に大火が起こり、市街地の大部分が焼失の憂き目にあう。
1889年、新潟町は市制施行で新潟市となるが、例の流作場新田は行政によって沼垂町に編入される。沼垂町民『200年来の恨みがやっと晴らせた!』
1897年、上越線沼垂駅開設。沼垂駅の方が、新潟駅よりも先にできたのである。
1904年、流作場新田に新潟駅開設。これを期に流作場は「駅前の市街地」へと劇的に変化していく。
1908年、再び新潟大火。
1914年、ついに長年ライバル関係にあった新潟市と沼垂町が手を結ぶ・・・ていうか、新潟市が沼垂町を編入。
以上、まぁ竜頭蛇尾だったがこんな新潟歴史物語です。もっと詳細な歴史が知りたかったらWikipediaでも見てください。
最後に。写真は俺がまだ高校生だった昭和51年の新潟市のマップだが、新潟駅の近くに「流作場」という町名があるのにお気づきだろう。そう、流作場新田は上記の急速な市街地化に伴って、「流作場新田○○」という字名を今風の町名にガンガン変えていったのだが、実はこの昭和51年の段階で、現在の南万代町の町民だけが『流作場の地名を消しちゃだめらて!』と断固反対していたため、ここだけ「流作場」という地名なのである。
翌昭和52年、唯一残っていた流作場は行政によって強引に「南万代町」に変更させられたのだ。