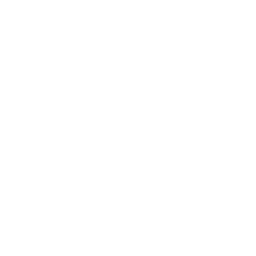306件のひとこと日記があります。
2017/06/23 12:35
ハードトレーニングの成功例を取り上げるな
ハードトレーニングの成功例を取り上げるなら、ハードトレーニングの失敗例と、軽いトレーニングの成功例と、軽いトレーニングの失敗例を並べて、メリットデメリットを検討した上で一頭の馬にあてはめられるか考えないと嘘だ。
キタサンブラックの記事を鵜呑みにして、「そうか、馬は鍛えれば鍛えるほどいいんだ!」と、そうしないことに文句を垂れ、怪我したらそれでも文句を垂れる間抜けが大量にわきそうだ。
まずは反例として、調整程度の調教に切り替えた途端に連勝し始めたゼンノロブロイあたりから取り上げてくんないかな。
-

YOU2012さん
最大五本をこなしたミホノブルボンが故障した上に、回復後も二度と走る気を起こさなかったこと。三本が常態化していたトウカイテイオーの度重なる故障。
また栗東の急激な躍進が坂路コースと結び付けられることで、ようやく「坂路ってハードトレーニングなんじゃないか?」という認識が、「一般層に」生まれた。
そして「坂路は強くなるが怪我もしやすい」という、それはそれで単純にすぎる理屈が浸透し、露骨に避ける調教師、一本二本を恐る恐る試す調教師など多様化し、ようやく坂路調教の加減が浸透し始めた。 -

YOU2012さん
新しい調教方法だからノウハウが蓄積されていない。
そのため調教量の加減は、馬の息の入りで判断された。
そして坂路調教はコースに比べて息の入りが早い傾向にある。
すぐに呼吸が回復するのを見て、「まだ走れるな」と、一本追加される。の繰り返しだった。
元々脚元に不安が残る馬が使用していたこともあって、走る疲労とは別物の脚元への負担は無視された。 -

YOU2012さん
ミホノブルボンの時代には、坂路三本追いは珍しくなかった。
なぜか? 単に「加減がわからなかった」からに過ぎない。
坂路調教は戦後から行われていたが、主に脚元に不安を持つ馬が使用するものだった。
トレーニングといえばひたすら走らせるだけの無能な時代、量をこなせない馬に、短い距離でも負荷をかけられるように坂道を利用した。というだけのもので、むしろ軽めの調教として認識されていた。
やがて栗東に長距離坂路コースが整備されると、「負担が小さい上に量もこなせる」と早合点した調教師たちは、通常のコースと同じ感覚で繰り返し坂路コースを走らせた。