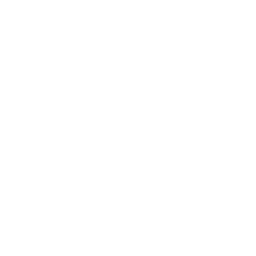136件のひとこと日記があります。
2018/03/06 00:53
たかがベロ出し、されどベロ出し、
競馬ファンであるからには馬のことぐらい少しは分からないと、と思い、独り身の時に乗馬をたまにしていました。だから馬の性格とか習性は私なりの理解の仕方で、何となく把握しているつもりです。そして昨日の弥生賞後のルメールのコメント(オブセッションが待機所を覚えていて戻ろうとした)には、さもありなんと思いました。こういうとこ確かにあります、お馬さん。覚えていたのを頭が良いとするのか、戻ろうとしたのをオバカとするのかは、人によりけりでしょうが、、、
たかが競馬、されど競馬とは、よく言ったものだと思います。冷静に考えたら、馬に人が乗って競争するのを、どの馬が勝つか真剣に考えて、お金を賭ける訳ですから。なんじゃそりゃ?と思います、普通。いつだか武豊がインタビューで、騎手であり続ける理由について聞かれて『だって馬に乗って競争するんですよ、面白いでしょ?』みたいに答えてたと記憶しています。
理由があるにせよ、気まぐれに行動する馬の競争に大勢の大人たちが一喜一憂するんですからね、これが面白くないはずがありません。
完璧な人間がいないように、完璧な馬もいないことは分かっています。しかし毎回同程度レベルのパフォーマンスを見せ、連戦連勝なんていう完璧な馬がいたとしたら、ぼくはきっと苦手に思うでしょうね。馬らしく気まぐれでいてほしいと願っているようです。クセが強く個性的であってほしいと。走るごとに新しさが加わてほしいと。ではテイエムオペラオーは?。この馬を見る度ぼくは牧場で鳴きながら飛び跳ねる仔馬をイメージしていて、まったく〈強い〉なんて連勝当時だって露にも思っていなかったんです。そもそも3歳時はあれでしたしね。逆にディープインパクトは〈強い〉とは思うものの、非常に冷めた思いで見ていました。お父さんとタイプは違えど、ダノンプレミアムに対しても似た思いです。まぁこうしたことは、人それぞれの感性の違いなのでうまく説明できませんけれども。
強い馬を見定めたところで、僕の人生に何も訪れやしない。
人は生まれたら後は死ぬだけ。せいぜい楽しみたいと思う。
だから気まぐれの偶然を祝福したい。
もう30年位前、ジョルジュ・バタイユの本を読んでいた時のことはよく覚えている。この本はぼく自身だと思った。この時から偶然こそを神様にしたんです。偶然だけがぼくに何かを運んでくれる。偶然は一瞬、または断片と捉え直しても構わないかもしれない。
そうすると自分が競馬の好きな理由が浮かび上がってきます。
競馬とは多くの偶然と、多くの一瞬と断片とを見させてくれるんです。降る雪が風の動きを見せてくれるように。
まだまだ幼稚で父の面影などないオブセッションが、よく訓練されて父を思い出させる優秀な2頭に勝てるとは正直思っていませんでした。しかしオブセッションに賭けることで何かが生じはしまいか?と思ったんです。
そして結果があれです。偶然や断片は積み重なっていく性質も持っています。それが物語とか人生と呼ばれています。あるいは運命とも。しかしそれは結果であって、何より切実なのは、まず目の前の偶然なのです。その偶然を掴み取ろうとすることが、つまりは芸術家であろうとすることが人の営みなのではないか?と、そう、アレキさん、あなたの掲示板への書き込みに誘発されて、長い能書きを垂れさせてもらいました。ありがとうございます。
オブセッションがベロを出したところから何かが動き始めたのだから、これにも感謝ですね。ありがとう。ベロンベロン、、、
-

スズヒロモリチャさんがいいね!と言っています。
-

ヒシチョンチョンさん
アレキさん、ナイスなご返事ありがとうございます。
いつもながらの誠実さに頭の下がる、見習いたい思いです。
アレキさんが現実理想主義であるのに対して、ぼくは直観空想主義ですからね。それにぼくは大衆に対して、もう諦めてしまってるんですよね、、、いけませんね。
大衆だって個の理性を高めることで、一人一人が違う考えを持ち、より成熟した集団になるはずなのに。それを考えると、やはりマスコミとメディアの責任は、ご指摘の通り大きいですね。まぁ分かっちゃいるんですが。
老けこまないで、まだまだ青く行かなきゃ、ですね。 -

アレキさん
応援してる馬だからって、負けをまで嘘まぼろし(シンドローム解釈)でぬりかためない。それなら勝った負けたで一喜一憂してるだけの人のがずっと目標が崇高で潔い。言い訳がないですもん。
…もちろん、競馬文化の理想的到達点はベッケンバウアーが嫉妬した人の姿であるのは同意ですが!(みんなに怒ってるのではなく、こういうまだまだ未熟な解釈があふれてる文化の中で、互い注意喚起しあうこともなく検討しあうこともなく、「こうしたら→こうだ」というまた新しいショートカット解釈、言ってみれば流行語のように、真実より売れる共感解釈を作ろうとしてる「記者とファンのなあなあサークル」の性根が、情けない…) -

アレキさん
手綱の動き一つでもこうして…日本の競馬ファンの感想は“誰に聞いたのか”判を押したように画一的。どこのゲームの“設定”を現実と混同してるのか…馬が馬券で人のパートナーではなくなってしまっている日本競馬にはそんなシーンが至る所にあります。
誰も目をつけているはずなのに自分から馬を見ず、見ようとせず、迷おうとせず、表情から聴き取ろうとせず、知ろうとしない人に、ましてやベロ(馬自身とも言えるもの…)まで「共感シンドローム化」されてゆけば、せっかくのサラブレッドもただの賭博場の機械に。
個性を記事にして、目で見ない人が共感度で是非を決めると行為ほど、個性の冒涜はないな、というのが一連の経緯に感じた私の思いでした。 -

アレキさん
全速力かは馬の表情を中心に全身を診る。馬は感情を耳であらわすからと耳だけみるのも技術を聞きかじった素人〜達者まで。こちらも全身の語感を拓いて診るものです。
全身全霊は手綱が動いているかどうかで判断するものではありません。手綱なんて、目が見えない人が仕方なく耳で状況を伺うとする手段と何も変わりません。なぜ己の目があるのにわざわざフィルターをつけるか。知る気がないからでしょう。楽を覚えたいからでしょう。
当たり前ですけど騎手だって手綱でなく馬を見て、感じて乗っています。私たちは運転をしなくていい、「見るだけ」でいいんですから特等席です。もっと(状況が)わかる立場にある。
(※乗ってないとわからないことがあるのはもちろんですが) -

アレキさん
フランツ・ベッケンバウアーの格言が“誰に”そして“どんな世論に”対してのレジスタンスであったか。ヒシチョンチョンさんとは文章が宛てる人(々)が違うだけですよ。馬を自分の目で見よ、個性を見よ、自分自身でパレットを描いてゆこう。という話ですから価値観は一緒だとして、誤解を恐れずにあれを記してます。
強い馬が馬群から突き抜け、騎手が手綱をピクリともさせずに最後流すと「スゲー!」と騒ぐのがオブセッション板で私が釘をさしたネット競馬の「共感シンドローム」です。実際は違う。馬の性格による。 -

人参かもしれない人さんがいいね!と言っています。