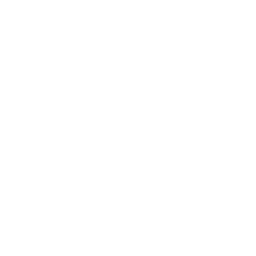4046件のひとこと日記があります。
2015/05/10 13:48
どういう変化が起きているのか? つらつら
どういう変化が起きているのか?
つらつらと書いてみます。30年間競馬をやっていて感じていることですから、細かいデータの裏打ちとは省きますよ。
競馬始めたときは、3歳(当時は4歳でしたね)全馬がダービーを目指していた。短距離で賞金を獲得した馬もダービー。
だから展開が速かった。こぞって前へ前へと短距離型が行くのでペースが速くなり、当然短距離型は足をためる訓練もしていないので、バテテ用なし。
それでは、真に選手権距離のある素質馬は賞金不足で出れないし、短距離型の馬の寿命も縮まっちゃうってことで、短距離路線が整備されて、NHKマイルもできた。もちろんダービーに出走制限のあった外国産馬用でもあったけれど。
これによって一定の路線すみわけが開始されたわけだけど、NHKには1200でバンバン行く馬も出てたわけね。そのときは短距離型もマイルなら大丈夫!って雰囲気はあった。そりゃダービーに比べればましだよね。でも結果としてびりっけつだったのが、せいぜい10着、よくて入着賞金が得られる8着に入れるのがいっぱいであり、勝つまでにはいかないってのが現実だったわけ。
つまり1200と2400が全然違うということと同じように、1200と1600もまた違うと。
でもそういう意識が関係者に浸透するまでは、やっぱりNHKには韋駄天がそろって出てきてたわけで、そうなるとやっぱりペースが上がっちゃう。で、後続も「スピードだけで逃げ切られる!」という意識から追いかけて、全体のタイムが上がり、上がりタイムがかかるサバイバル戦になる。
結果として、スタミナ満点の馬がラスト「ばてない脚」を伸ばして上位を独占するってのがしばらく続いた。
この時期に「東京マイルは中距離適性の馬が勝つ」っていう定説が流れた時期。実際そうだったよね。
典型的なのはダノンシャンティが驚異のタイムで勝った年
勝ちタイムが1.31.4
すごいよね。でも結果何が起きたかっていうと、この年に上位を独占した馬は、心身共にボロボロだよね。ダノンシャンティなんて、その後、勝ってないし、わずか三戦だけして、勝ちもなく引退でしょ?二着ダイワバーバリアンもスワンSを17着しただけで引退。三着のリルダヴァルは勝っているけどオープン特別だけ。四着サンライズプリンスも4戦で引退。勝ちはなし。31秒台で走った馬は軒並みダメージがでかく泣かず飛ばずだった。
このレースが転機になったのかどうかわからないけど、いくら勝つためとはいえ、こんなハイペースを前を追いかけて好着順を取りにいったところで、いいところはないね、という流れになっていったんじゃないかな。
同時に短距離タイプは、「やっぱ1200とマイルは違うぜ」というのに気付き始めた。要するに1200は「とにかく飛ばす。足を貯めてラストに賭けたところで、前半じっくり行った分水をあけられた距離をを挽回するのは難しい」距離で、1600は「2400ほどではないにしても、ある程度ためる」という違いがあるわけで・・・
こうなると、さらにすみわけが進んで1200、欲張っても1400という短距離志向とマイル志向に分かれていく。
その結果、何が起きるかというと1600において、バカみたいな前半にならなくなるので、「ばてないスタミナ」よりは「平均的なスピード能力」の方が必要になってくるんだな、これが。