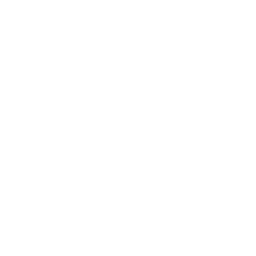4046件のひとこと日記があります。
2018/05/25 12:45
距離別スタミナの考え方 実務編
まず、ベースとして捉えなくてはならないのは、有酸素運動のマックススピード値だ!
この値(スピード)は、個体により先天的にも後天的にも優劣がでるが、
ポイントとなるのは・・
まず
単位時間当たりの、身体中に送り込める酸素量(最大酸素摂取量)
これは先天的のものに対してトレーニングでの上乗せが可能。
次に
ミトコンドリア(母系ファミリーナンバー毎の遺伝的素質)の性能
これは、完璧に遺伝
そして
走り方(フォームの効率性)、体の柔らかさ、筋力
これらは、先天的なものの比重は高いが、後天的に鍛えられるものもある。
まあ、これらの要素に依存するので、全馬一律のスピードを示す訳にはいかないが、
私の感覚では、概ね
当該馬のキャンタースピードかな?
と、思ってます。
ハロン15秒程度前後なら、かなり長い距離走り続けられると思います。
それが、
14.7秒の馬もいれば15.5秒の馬もいるでしょう。
その有酸素運動のマックススピードが、速ければ速いほど
中長距離は得意だと思っていいです。
なぜならそのマックススピードこそ、走行中のエネルギー(酸素)摂取によって生み出される、基礎スタミナスピードになるので、それが高ければ高いほど
実際に表から見えるスピード(ハロン12秒のときもあれば、10秒台の鬼脚のときもある)を出すための、上乗せ無酸素運動の量を
セーブできるので、結局はそのことが、いかにながい距離を速く走れるか?
に繋がるので!
例えば
有酸素運動マックススピード
14.5秒の馬も
15.5秒の馬も
その有酸素運動をベースに「使いっきりのエネルギーである無酸素運動を上乗せして」
ハロン12秒の追走を可能にするわけですが、当然のように
有酸素運動最大スピードの速いほうが、上乗せしなきゃいけない無酸素運動の量は少ないんです。
ここで言う
有酸素運動マックススピードとは、決して外から見える「その馬の最高速度とは厳密な意味では関係ない」ので、誤解なきよう。
ウルトラマッチョ馬の筋肉モリモリ馬の
有酸素運動マックススピードが、
16秒で
かたや、スリムな非力に見えるステイヤー血統のスタミナ馬の
有酸素運動マックススピードが、
14秒と圧倒的に速かったとしても、200メートルの直線競馬の、
超全力疾走レースにおいては、有酸素運動スピードが圧倒的に劣る前者が、
10秒チョイで走れるけど、
後者は
11秒を切ることすらできない、というのは往々にして発生することだ。
無酸素運動がどれだけ上乗せできるか?は、無酸素運動がスタート以降、消費すれば減ることはあっても増えるものでない以上、
距離が長くなって、無酸素運動上乗せ期間が長くなればなるほど、スタミナはより多く費やされるし、
ペースが速ければ速いほど、上乗せする無酸素運動エネルギー量(上乗せしなければならない加速パワー)は、大きくなり、スタミナはより多く費やされる。
これが基本的なメカニズムなんだけど、なぜ2000と、2400という
100対120
という一見、近いカテゴリーに見える二つの距離の間に
大きな差があるのは(必要とされる走力とスタミナ)、
実は
一旦、加速してスピードに乗れば、「しばらくは慣性の法則によって、惰性でスピードが維持される」
ということが関係している。
ここは、かなり科学的アプローチになるので、また後で