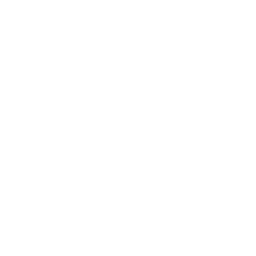4046件のひとこと日記があります。
2018/05/25 13:55
距離別に必要なスタミナを捉えるためのメカニズム理解
大雑把なメカニズムは、こういうことだと思ってる。
※因みに有酸素運動と無酸素運動は、理解されている前提で書いてます。わからない方は言ってください。簡単に補足しますから。
まず、スタートからハロン12秒前後に向けてのダッシュプロセスは、
500キロからの巨体を
スピードゼロから
起動するエネルギーであり、極大。ここは、無酸素運動による巨大エネルギー爆発。
で、一定のところから、有酸素運動も同時に動員される。
で、ここからひとつ、大きな山場
みんなが、短距離ダッシュする局面考えて。
よーいどん
からダッシュしてさ、その後、30メートル位のところで、ぱったり止まりますか?
質問悪いかな?
要するに、30メートルから先の行程も走り続けようと力んだり、脚を動かそうとしなくても、
止まらないでしょ?
泥沼とか、雪の上なら別だけど、
芝とかコンクリートの上なら止まらないよね。
くどいけど、これが慣性の法則
脚の裏の接地面の抵抗とか空気抵抗とか、動かす脚自体の内部の筋肉そのものの摩擦抵抗とか、そういうもんが、抵抗がゼロなら
スピードは、一切落ちない。理論的には
でも、摩擦はゼロではないから、減速はして、どこかで、スピードゼロにはなる。
でも、スタート後に200メートル位物凄い勢いで加速したら、500キロもある馬の時速70キロの進行方向へのベクトルエネルギーって、凄まじくて、まあ、走ろうとしなくても、数百メートルは止まらない。
その止まらない区間に、
ハロン12秒にするために上乗せする無酸素運動のエネルギー量と、
1000メートルを過ぎてからあたりには、もうスタートダッシュの惰性など期待できず、
そこから先、ハロン当たり12秒台のラップを刻むためのエネルギー量は、スタート直後におなじことをする際のエネルギー量よりでかいはず。
多分!
おなじ12秒ラップのとはいえ、動員しなければならない無酸素運動エネルギー量は
距離が伸びれば伸びるほど、
その距離の長さに比例して増加するだけにとどまらず、単位距離あたりに必要な総エネルギー量自体が増えるはずで、
2000と2400において、おなじ平均ラップだとしても、動員が必要なエネルギー量は、
100対120どころではないはず!